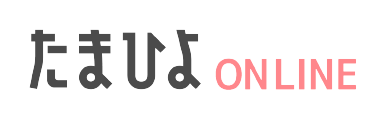子どもの脳を育む住環境で大切なのは「安心感と刺激のバランス」
みなさん、それぞれにこだわりがありますね。ここからは、実際に3人のお子さんを育てながら研究を続けている東北大学大学院情報科学研究科准教授の細田千尋さんにお話をお聞きします。脳科学の観点から、子育てしやすく、子どもの成長にいい影響を与える住環境の作り方について教わりました。
「子どもが成長する住環境は、単に『住みやすさ』だけではなく、その脳の発達にも深く関わっています。
特に、感情を司る扁桃体、記憶力や学習能力に関わる海馬、そして計画性や自己制御を担う前頭葉は、住環境の影響を強く受けます。これらの脳の部位に良い影響を与える住環境をどのように整えるべきかを考えてみましょう。
リビングは、家族が自然に集まり、コミュニケーションを育む場です。
リビングでの親子の会話やスキンシップは、子どもの不安な気持ちを落ち着かせ、感情を安定させる働きをします。
不安や恐怖の気持ちがある時、脳の中では扁桃体といわいれるところが活動しています。スキンシップや子どもとの対話で、それらの気持ちを和らげることはとても大事なことです。
子どもにとって、自分は愛されている、という感情を持ち愛着形成ができていることは、非認知能力の発達に影響することが研究からわかっています。
また、親が近くで見守るリビング学習は、計画性や集中力を支える前頭葉の発達に適した環境です。
前頭葉は、計画性や自己制御、判断力を司る脳の重要な部位です。この部分の発達は脳の中で一番遅く、青年期くらいまでの間に成熟していきます。つまり、幼児期から高校生くらいまで、前頭葉はまだまだ成長中、言い換えれば、未成熟なのです。
そのため、人の目があることで、未熟な前頭葉を補いながら勉強を進めることができるリビングを中心にした学びの場を作ることは有効でしょう。
リビングを広々と感じられるように設計し、自然光が差し込む明るい空間を作ることは、脳内でセロトニンが分泌される助けとなります。これは、子どもの情緒の安定や集中力の向上に寄与します。
リビングに、テレビやゲームなどの音が常に入っている環境は、気が付かないうちにストレスとなり、前頭葉の働きを妨げる可能性があります。
適切に配置して、子どもが遊びと学びの切り替えをしやすい空間を作ることが重要です。
さらに、整理整頓された環境は、秩序感を育みます。
子どもが自分で片付けられる収納スペースを用意することで、計画性や自己管理能力をサポートできます。
住環境の中で、子どもの五感に適度な刺激を与えることは、脳の発達にとって非常に効果的です。
自然光が差し込む窓辺や、壁紙に寒色系(グレーやライトブルー)を採用することは、リラックス効果を高め、記憶力や集中力を高めます。
また、木の家具や観葉植物といった自然素材を取り入れることは、視覚や触覚に心地よい刺激を与え、脳をリラックスさせます。
運動や遊びの場もまた、子どもの脳にとって重要な意味を持ちます。特に海馬は運動や遊びによって活性化され、記憶力や学習能力の向上に寄与します。
広いリビングや庭で自由に動き回れる環境を整えることが、子どもの健やかな発達を支えるポイントです。家庭内に簡単なアスレチックや遊具を設置するだけでも、子どもが楽しみながら体を動かせる場を提供できます。
認知機能、非認知機能、それらは関連しながら発達していくのですが、どちらもキーとなるのは前頭前野の発達です。この発達が10代後半にかけてまで続くことを意識しながら、脳を育てる住環境ができると良いですね」(細田千尋さん)
キーとなる前頭前野は中学生や高校生になってもまだまだ発達過程なのですね。ぜひ参考にしてください。
(取材・文/橋本真理子、たまひよONLINE編集部)
細田千尋さん

PROFILE)
医学博士・認知科学者・脳科学。東北大学加齢医学研究所及び、東北大学大学院情報科学研究科准教授。内閣府のムーンショット研究目標9プロジェクトマネージャー(わたしたちの子育て―child care commons―を実現するための情報基盤技術構築)。3児の母。
※文中のコメントは「たまひよ」アプリユーザーから集めた体験談を再編集したものです。
※記事の内容は2024年12月の情報であり、現在と異なる場合があります。