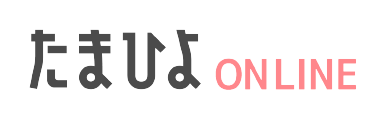小児科医が教える、脳にいい影響がある朝ごはん。朝ごはんしだいで、学校生活が楽しくなる!?

-
ストレスのせいで、緊張するとおなかが痛くなったり試験前に便秘になったり・・・。経験として、心(脳)の状態が腸に影響を与えることを理解している方も多いのではないでしょうか?
「食事を見直し、腸内環境が整うと脳にいい影響があるんですよ」と話すのは小児科医の工藤紀子先生。そこで、脳と腸の関係性と腸内環境を整える食事について聞きました。腸内環境が整うと脳もいい状態になり、学習も進むとか・・・。キーワードは「ねばねば」と「白より茶色」です!ドキドキ緊張する場面では腸活ごはんが効く

――腸は「第二の脳」とも呼ばれています。脳にどんな影響を与えているのでしょうか?
工藤先生(以下敬称略) 脳と腸には互いに影響を及ぼし合う「脳腸相関」という関係性があり、ストレスがかかるとおなかの具合が悪くなる、というのもその一例。逆に腸の調子がいいと、ポジティブな気持ちになったり物事に集中できたりすることが最近わかってきました。
環境がガラッと変わる新学期や学校行事、大事なテストがあるときなど、子どもがドキドキするような場面に備え、日ごろから腸内環境を整えるのはもちろん、忙しい・食べられないからと食事を抜かず、腸を意識したメニューを用意してあげるといいんです。
――腸を整えることから子どもを応援するんですね。具体的には食事の内容でしょうか?
工藤 腸内環境を整える食事の内容について「シンバイオティクス」と呼ばれる組み合わせが注目されています。
シンバイオティクスの「シン」は一緒に、という意味ですが、善玉菌となる「○○菌」がつく食べ物(=プロバイオティクス)と菌のエサになるもの(=プレバイオティクス)、この2つを一緒にとることにより、相乗効果が得られ、腸内の善玉菌が増えやすくなるという考え方です。
「プロバイオティクス」には、乳酸菌、ビフィズス菌、納豆菌・麹菌などの有用菌、「プレバイオティクス」には食物繊維やオリゴ糖があげられます。
食物繊維は野菜、果物、海そう類、きのこ類、豆類などいろいろな食材に含まれていますが、「ねばねばしたもの」にはとくにプレバイオティとして働く水溶性食物繊維が豊富です。おくら、モロヘイヤ・山いも、海そう、果物ではバナナ・りんご・いちじく・プルーンなどがあげられます。
ねばねばといえば納豆ですが、納豆には納豆菌だけでなく食物繊維も含まれているので、ぜひ積極的にとってほしい食品です。
このほか腸内で食物繊維を分解・発酵する過程でできる短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)は悪玉菌を抑えるはたらきがあり、腸内環境の改善に有効な物質として注目されています。続きを読む